2025年03月24日 18:45

2025年2月11日
たけしが昨年11月から体調が悪い。
てんかん薬の変更
眠剤の減薬
苦手な冬
が重なって、絶不調。
体重も3キロ、筋力が落ちた。(ふくらはぎ回りで1.5センチ減!)
睡眠、食事がとれない→風邪をひく→治らない
このループまさに2歳頃と全く同じ。
ずっと咳き込みつらそう。
だからといって一気に回復しない。
とにかく第一は、睡眠
その次が、
栄養補給。
全ては睡眠から始まるので、4日前から自宅で療養中。
本当だったらシェアハウスに戻すのだけれど、このループを断ち切らないと。
同時に私も寝れないけど。まあ仕方がない。
ヘルパー事業者ウルトラもサポートしてくれてます。
しかし、やはり体調不良は本当に難しい。
何がどうやら全くわからない。みんなで悩んでます。
不機嫌、イライラ、ご飯を食べない、暴れる、こだわり、咳込みが同時に起こる。
普通が通用しないたけし。(普通はならば自らおとなしくするのだが、かえって暴れる。)
明日、
てんかんセンター受診と、
内科受診
この時期は、成年後見人報告書作成もあり、、今週中に出さないといけない。
(私はたけしの成年後見人でもある。たけしの父が亡くなってから、相続でそうしなくてはいけなくなった。ほんと、私たちにとっては悪法だと私は思う)
書かなけれいけない原稿もある。
こういう時に限って度胸がすわるというのか。これも長年の積み重ねなのか?
それにしても、たけしは全国でも難しい部類に入る人だと思う。
そういう人の自立を私たちは実行している。
ものずこい学びを身を挺して提供してくれている。
やっぱりたけしはパイオニアだ。。
どっかで発表したいぐらい。
研究者の皆様、どうでしょうか?
写真はタンが絡んで飲み込めなくなってしまっているたけしの栄養補給を考えて買ってきた粉ミルク。
なんか色々思い出すなぁ。
2025年2月13日
今、たけしが調子悪くて家にいる。
今日で7日目。
ご飯やドロドロの流動食をぶちまけられたり、ガラスや戸棚、テレビをバンバン叩いて破壊されそうになったり。
数時間前、ちょっと目を離した隙に、沸騰式の加湿器を投げて熱湯を浴びて、裸にして、喘息で養生しているにもかかわらず、この寒いのに冷水浴びさせて。
また肺炎になったらどうしようと思いながら、体をチェックし、お湯に変えて温めて、体を拭いて、パンツをはかせて、洋服を着せて・・。
その間暴れるから、まるで格闘技。
私はこういうとき、めちゃくちゃ切れてるし、情けなくて、切なくなる。
60過ぎの女が、うんちやおしっこや、暴れる30近くの息子とバトルしている姿は、世間的には、悲惨なのかもしれないけど。
私は、これが「生きていること」だと思う。
さすがに続くと、神経と体力削られて行くけれど。そして最近は、自立生活を始めているから、年中こうではないが。しかし、こういう時間は私の現実の中にはある。
そして、自分のことを惨めだとは思ったことがない。(特殊な能力?なのかもしれないが。)
私はこれこそ
生きている証だと思う。
人生なんて、結局、こんなもんなのよ。
とも。
さあ、今から寝かすぞ〜!
2025年2月14日
たけしの自立生活は、レッツのスタッフの涙ぐましい努力と叡智によって完成しつつある。
しかし、たけしの健康管理だけはスペシャル難しい。
私も支援者の一人として参画しながら一緒に悩んでいる。
シェアハウスは共同生活だから時として自宅のほうがいい時もある。
特に病気のとき。
そして私が一人で見ているのではなく、皆さんにも手伝ってもらっている。
しかし、本人が全く治そうと思っておらず、養生しない。
だから治るものも治らない。
で、こじらす。
最後の砦が自宅。
自立生活において、家族の使い方としてこれは正しいと私は思う。
これは5年の歳月をかけて、様々な葛藤と議論と対話の中から私たちが編み出してきた一つの方法。
時間はかかるものだ。
写真はキイチヘルパーが自宅で支援。
2025年2月21日
今週、たけしはシェアハウスに戻った。
そして、ヘルパーさん達の創意工夫でなんとか、睡眠、栄養をギリギリ確保。
少しづつ、固形物も、口にしてくれるようになってきた。
てんかん発作、薬の副作用による食欲不振、下痢、体重減少、体調不良からの肺炎、喘息発作、さらに花粉症。
と、とにかくトリプルパンチ。
そんな状態の中、私も含めて、訪問介護、訪問医療、アルスノヴァ、ウルトラが連携しながら彼の自立生活を支えるシステムが作られていく。
これってすごいことだ。
この轍が、重度知的障害者の自立生活の大切な知見として後進たちに活用できるように、私たちもまとめていかないといけない。
いつもだけど、たけしはチャレンジャー。身を挺して道なき道を切り開いていく。
2025年3月24日
壮の体調
2月21日シェアハウスに戻り、そこから一週間、レッツスタッフの皆さんの献身的な支援もあって、3月に入ってやっと調子が戻ってきた。
そして3月7日、てんかんセンター―受診。てんかん薬の副作用として食欲減退はやはり支援や介護を難しくしている状況を訴え、薬を1日5ミリから4ミリに減らすことになった。
これで大きなてんかん発作が起きなければそれでよしとするが、難しいようであれば、もう一度手術を考えなければいけない・・・。
その後、やっと固形物に興味を示すようになった。(てんかん薬の恐ろしさも改めて知る)
この2週間、結構調子もよく、表情もいい。アルス・ノヴァのスタッフたちもやっと平穏な気持ちが戻ってくる(わたしも)。
3月21日の受診では、このまま様子を見ることになる。
そして懸案である眠剤の減薬を来月から始めましょうと先生から。
3月24日、今また家に帰ってきている。
今度は今はやっているウイルス性胃腸炎に罹患したようだ。
幸い下痢だけのようだが、ヘルパーさんのけがもあって、3月はシフトがかなり大変だった。それもあって今日は自宅療養に。他の皆さんにうつっても困るしね。
ヘロヘロしながら、昏々と寝るたけし。
案の定、ご飯を口にしない。(また始まったか??)
2週間と安定した体調がないたけし。
よく考えたら生まれてからずっとこんな感じ。
常に体調が変化する。安定感がない。
何でも口に入れてしまうし、外に転がっている石をなめて回っているようなものだから、いろいろなものが体に入っているんだろう。
そして言葉もないから、暑いのか、寒いのか、どこが痛いのか、調子が悪いのかも皆目わからない。
すべてを介助者にゆだねているのだから、それは体調も安定しないだろう。
ほんとよく生きていると思う。
もし私が一人で介護していたら、相当追い詰められていたと思う。
それこそ将来を悲観して・・、みたいなことも冗談ではなく、簡単に起こっているだろう。
と同時に、自分で施設を立ち上げてしまったからこそ、こうした人たちを支えていく重さみたいなものも感じずにはいられない。
時々怖くなることも私にだってたまにある。
だからこそ、明るく、楽しく、クリエイティブに、支えていく「福祉」を考え、実験し、作り上げていかないとだな。
早く治りますように。
壮の体調 2025年2月11日~3月24日≫

2025年2月11日
たけしが昨年11月から体調が悪い。
てんかん薬の変更
眠剤の減薬
苦手な冬
が重なって、絶不調。
体重も3キロ、筋力が落ちた。(ふくらはぎ回りで1.5センチ減!)
睡眠、食事がとれない→風邪をひく→治らない
このループまさに2歳頃と全く同じ。
ずっと咳き込みつらそう。
だからといって一気に回復しない。
とにかく第一は、睡眠
その次が、
栄養補給。
全ては睡眠から始まるので、4日前から自宅で療養中。
本当だったらシェアハウスに戻すのだけれど、このループを断ち切らないと。
同時に私も寝れないけど。まあ仕方がない。
ヘルパー事業者ウルトラもサポートしてくれてます。
しかし、やはり体調不良は本当に難しい。
何がどうやら全くわからない。みんなで悩んでます。
不機嫌、イライラ、ご飯を食べない、暴れる、こだわり、咳込みが同時に起こる。
普通が通用しないたけし。(普通はならば自らおとなしくするのだが、かえって暴れる。)
明日、
てんかんセンター受診と、
内科受診
この時期は、成年後見人報告書作成もあり、、今週中に出さないといけない。
(私はたけしの成年後見人でもある。たけしの父が亡くなってから、相続でそうしなくてはいけなくなった。ほんと、私たちにとっては悪法だと私は思う)
書かなけれいけない原稿もある。
こういう時に限って度胸がすわるというのか。これも長年の積み重ねなのか?
それにしても、たけしは全国でも難しい部類に入る人だと思う。
そういう人の自立を私たちは実行している。
ものずこい学びを身を挺して提供してくれている。
やっぱりたけしはパイオニアだ。。
どっかで発表したいぐらい。
研究者の皆様、どうでしょうか?
写真はタンが絡んで飲み込めなくなってしまっているたけしの栄養補給を考えて買ってきた粉ミルク。
なんか色々思い出すなぁ。
2025年2月13日
今、たけしが調子悪くて家にいる。
今日で7日目。
ご飯やドロドロの流動食をぶちまけられたり、ガラスや戸棚、テレビをバンバン叩いて破壊されそうになったり。
数時間前、ちょっと目を離した隙に、沸騰式の加湿器を投げて熱湯を浴びて、裸にして、喘息で養生しているにもかかわらず、この寒いのに冷水浴びさせて。
また肺炎になったらどうしようと思いながら、体をチェックし、お湯に変えて温めて、体を拭いて、パンツをはかせて、洋服を着せて・・。
その間暴れるから、まるで格闘技。
私はこういうとき、めちゃくちゃ切れてるし、情けなくて、切なくなる。
60過ぎの女が、うんちやおしっこや、暴れる30近くの息子とバトルしている姿は、世間的には、悲惨なのかもしれないけど。
私は、これが「生きていること」だと思う。
さすがに続くと、神経と体力削られて行くけれど。そして最近は、自立生活を始めているから、年中こうではないが。しかし、こういう時間は私の現実の中にはある。
そして、自分のことを惨めだとは思ったことがない。(特殊な能力?なのかもしれないが。)
私はこれこそ
生きている証だと思う。
人生なんて、結局、こんなもんなのよ。
とも。
さあ、今から寝かすぞ〜!
2025年2月14日
たけしの自立生活は、レッツのスタッフの涙ぐましい努力と叡智によって完成しつつある。
しかし、たけしの健康管理だけはスペシャル難しい。
私も支援者の一人として参画しながら一緒に悩んでいる。
シェアハウスは共同生活だから時として自宅のほうがいい時もある。
特に病気のとき。
そして私が一人で見ているのではなく、皆さんにも手伝ってもらっている。
しかし、本人が全く治そうと思っておらず、養生しない。
だから治るものも治らない。
で、こじらす。
最後の砦が自宅。
自立生活において、家族の使い方としてこれは正しいと私は思う。
これは5年の歳月をかけて、様々な葛藤と議論と対話の中から私たちが編み出してきた一つの方法。
時間はかかるものだ。
写真はキイチヘルパーが自宅で支援。
2025年2月21日
今週、たけしはシェアハウスに戻った。
そして、ヘルパーさん達の創意工夫でなんとか、睡眠、栄養をギリギリ確保。
少しづつ、固形物も、口にしてくれるようになってきた。
てんかん発作、薬の副作用による食欲不振、下痢、体重減少、体調不良からの肺炎、喘息発作、さらに花粉症。
と、とにかくトリプルパンチ。
そんな状態の中、私も含めて、訪問介護、訪問医療、アルスノヴァ、ウルトラが連携しながら彼の自立生活を支えるシステムが作られていく。
これってすごいことだ。
この轍が、重度知的障害者の自立生活の大切な知見として後進たちに活用できるように、私たちもまとめていかないといけない。
いつもだけど、たけしはチャレンジャー。身を挺して道なき道を切り開いていく。
2025年3月24日
壮の体調
2月21日シェアハウスに戻り、そこから一週間、レッツスタッフの皆さんの献身的な支援もあって、3月に入ってやっと調子が戻ってきた。
そして3月7日、てんかんセンター―受診。てんかん薬の副作用として食欲減退はやはり支援や介護を難しくしている状況を訴え、薬を1日5ミリから4ミリに減らすことになった。
これで大きなてんかん発作が起きなければそれでよしとするが、難しいようであれば、もう一度手術を考えなければいけない・・・。
その後、やっと固形物に興味を示すようになった。(てんかん薬の恐ろしさも改めて知る)
この2週間、結構調子もよく、表情もいい。アルス・ノヴァのスタッフたちもやっと平穏な気持ちが戻ってくる(わたしも)。
3月21日の受診では、このまま様子を見ることになる。
そして懸案である眠剤の減薬を来月から始めましょうと先生から。
3月24日、今また家に帰ってきている。
今度は今はやっているウイルス性胃腸炎に罹患したようだ。
幸い下痢だけのようだが、ヘルパーさんのけがもあって、3月はシフトがかなり大変だった。それもあって今日は自宅療養に。他の皆さんにうつっても困るしね。
ヘロヘロしながら、昏々と寝るたけし。
案の定、ご飯を口にしない。(また始まったか??)
2週間と安定した体調がないたけし。
よく考えたら生まれてからずっとこんな感じ。
常に体調が変化する。安定感がない。
何でも口に入れてしまうし、外に転がっている石をなめて回っているようなものだから、いろいろなものが体に入っているんだろう。
そして言葉もないから、暑いのか、寒いのか、どこが痛いのか、調子が悪いのかも皆目わからない。
すべてを介助者にゆだねているのだから、それは体調も安定しないだろう。
ほんとよく生きていると思う。
もし私が一人で介護していたら、相当追い詰められていたと思う。
それこそ将来を悲観して・・、みたいなことも冗談ではなく、簡単に起こっているだろう。
と同時に、自分で施設を立ち上げてしまったからこそ、こうした人たちを支えていく重さみたいなものも感じずにはいられない。
時々怖くなることも私にだってたまにある。
だからこそ、明るく、楽しく、クリエイティブに、支えていく「福祉」を考え、実験し、作り上げていかないとだな。
早く治りますように。
2025年01月03日 13:16

60歳を過ぎて、新たに自分の人生を作り出す
年末。
夫は掃除が嫌いだった。
私は無類の掃除好き。
だから毎年大喧嘩。
いつまでもやめない私。
はやく終わってゆっくりしたい夫。
そして汚すだけのたけし。
しぶしぶ私に付き合っている娘。
今、年末は一人で掃除している。
家族4人がいた家は広いばかりで、ガラスだけで30枚以上ある。
ひたすら労働である。しかしこれが私は好きである。おまけにきれいになる。
文句言う人もいないし、自分のペースでできるから、はかどること!
こんなことなら家族がいたころから一人で掃除すればよかった。
夫と子供は買い物か旅行にでも行ってもらって、思う存分掃除していればよかったのだ。
なんでそういう自由な発想が、あのころ生まれなかったのだろうか。
今みたいにたけしを預かってくれる人も、面倒見てくれるところもなかったから仕方がなかったのだが。
気持ちの余裕がなかったのは正直、ある。
でも一番の原因は、「掃除はみんなでするもの」という全体主義的家族像が私を縛っていたように思う。
家族だから当たり前。が私には結構あって、自分も家族も苦しんだように今思う。
そして共同体としての結束よりも、個々の自由や、居心地の良さを重視していれば、もう少し穏やかな年末があった。
まあ、人生は後の祭りのことが多くある。
60歳を過ぎて、一人で生きていくにしても誰かにお世話になるとしても、自分のやりたいことを自分でちゃんと選択してそれを自分で守る気持ちが大切なんだろう。
誰かに期待すること。それは希望や愛にもつながるが、過大になった途端、束縛や自分の自由も奪うことになる。(この塩梅は難しい)
そのためには、常に自分を軸に据えながら、できること、できないこと、そしてできないことをちゃんとあきらめる。
家族っていうのはここに「家族だから」と押し付けられてしまうのだが、それはやはり誰かを不幸せにするように思う。
究極、人は一人なのだという孤独を引き受けながらその中で、どう幸せになれるかを考えるのだと思う。
60を過ぎて、一人になってみて、私はひとつずつ、家族の呪縛から解放されていく。
そしてもう一度新しい自分の生き方をつくりだしていくんだろう。
それは結構楽しい作業なのかもしれないと思えてきた。
2025年。
どんな自分に出会えるのか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今レッツで人材を募集してます。
こちらもよろしく!
https://cslets.net/wp/recruit?fbclid=IwY2xjawHkQzJleHRuA2FlbQIxMAABHTsJJ1qBKj_gMaJ9xPwt39f6MpoWIrh4ra82H3v0OSZOoZnLKOxR5gRlRw_aem_hbBOFueL-u6L1ou7PkiUbg
私の自立~60歳を過ぎて、新たに自分の人生を作り出す?≫

60歳を過ぎて、新たに自分の人生を作り出す
年末。
夫は掃除が嫌いだった。
私は無類の掃除好き。
だから毎年大喧嘩。
いつまでもやめない私。
はやく終わってゆっくりしたい夫。
そして汚すだけのたけし。
しぶしぶ私に付き合っている娘。
今、年末は一人で掃除している。
家族4人がいた家は広いばかりで、ガラスだけで30枚以上ある。
ひたすら労働である。しかしこれが私は好きである。おまけにきれいになる。
文句言う人もいないし、自分のペースでできるから、はかどること!
こんなことなら家族がいたころから一人で掃除すればよかった。
夫と子供は買い物か旅行にでも行ってもらって、思う存分掃除していればよかったのだ。
なんでそういう自由な発想が、あのころ生まれなかったのだろうか。
今みたいにたけしを預かってくれる人も、面倒見てくれるところもなかったから仕方がなかったのだが。
気持ちの余裕がなかったのは正直、ある。
でも一番の原因は、「掃除はみんなでするもの」という全体主義的家族像が私を縛っていたように思う。
家族だから当たり前。が私には結構あって、自分も家族も苦しんだように今思う。
そして共同体としての結束よりも、個々の自由や、居心地の良さを重視していれば、もう少し穏やかな年末があった。
まあ、人生は後の祭りのことが多くある。
60歳を過ぎて、一人で生きていくにしても誰かにお世話になるとしても、自分のやりたいことを自分でちゃんと選択してそれを自分で守る気持ちが大切なんだろう。
誰かに期待すること。それは希望や愛にもつながるが、過大になった途端、束縛や自分の自由も奪うことになる。(この塩梅は難しい)
そのためには、常に自分を軸に据えながら、できること、できないこと、そしてできないことをちゃんとあきらめる。
家族っていうのはここに「家族だから」と押し付けられてしまうのだが、それはやはり誰かを不幸せにするように思う。
究極、人は一人なのだという孤独を引き受けながらその中で、どう幸せになれるかを考えるのだと思う。
60を過ぎて、一人になってみて、私はひとつずつ、家族の呪縛から解放されていく。
そしてもう一度新しい自分の生き方をつくりだしていくんだろう。
それは結構楽しい作業なのかもしれないと思えてきた。
2025年。
どんな自分に出会えるのか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今レッツで人材を募集してます。
こちらもよろしく!
https://cslets.net/wp/recruit?fbclid=IwY2xjawHkQzJleHRuA2FlbQIxMAABHTsJJ1qBKj_gMaJ9xPwt39f6MpoWIrh4ra82H3v0OSZOoZnLKOxR5gRlRw_aem_hbBOFueL-u6L1ou7PkiUbg
2024年10月20日 10:13







今年私の母、高木淑子さんが88歳の喜寿。
女性の平均寿命が87歳の時代。
病気一つせず、思ったことをズバズバいうところも全く変わることなく顕在。
子どものころから、迫力のある人(ロックともパンクともいう)だとは思っていた。
時には理不尽であったり、はたまた哲学者的であったり。
そして今でも私や妹弟にも多大な影響を与えている。
自分に正直に生きるというのは時に回りも傷つくし、本人も傷つく。それでも忖度なしに前に進む。
生き方としては生きづらいと思う。年をとって少しはおとなしくなったけれど、それでも何かをぶっ壊しても前に進む。(相変わらず理不尽)
(現在、弟と生活しているのだが、どんなに大変かは想像できる。カズさん、ありがとう!)
そいて、10月14日、静岡に住む母を浜松に招いて、主に久保田瑛(孫)夫婦がアテンドしてお祝いの会が設けられた。そして、もう一人の孫である壮(たけし)も参加。
姉からの通達は「おばあちゃんに何かプレゼントを用意すること」
そしてたけしの支援者とたけしでかなり悩んだらしい。
相手は淑子さんである。気に入らなければ「いらない」と突き返される。
さあどうするのか。
浜名湖の景色が一望できるレストランでの会食。お客さんが引いてほぼ貸し切り状態になったところで正装したたけしと今日の支援をしてくれているフキ子さんとヨーイチくんと登場。
そして、レストランが用意してくれたケーキと瑛さんの花束と、そしてたけしから一輪挿しをプレゼント。
その姿に、私も本当に驚いた!
私の知っているたけしじゃない。
淑子さんをじっと見つめているたけし。そこには、28歳の若々しい青年がいた。
「僕はもうちゃんと自立しているよ。おばあちゃん。」と。
なんと凛々しく、たくましいことか。
そして淑子さんが泣いた。
私もほとんど見たことがない母の涙。
それはどんな感情が去来したのかはわからない。
孫二人がちゃんと自分の人生を歩んでいる。もう、子どもではない。
その安どの涙なのか。
特に「障害」についてクラシカルな通念からなかなか脱却できない感情への懺悔なのか。(ここだけは保守的であった)
そして、この会を企画の秀逸さに感嘆した。
瑛はたけしが一人の大人として誰かに「プレゼント」を手渡すことにこだわっていた。
常に庇護を受ける存在ではなく、誰かに何かを「贈与」することの必要性を訴えていた。
話を聞いていてもいまいちピンとこなかったのだが、こういうことだったのか。
誰かに何かを受け渡す。それを自覚的に行うことで初めて「自立」が成立するのか!
そしてこの会と、たけしの一輪挿しは、祖母に確実に何かを手渡した。
それは連綿と続く命のつながりの中に自分もいて、次の人に贈与していくこと。
時に「自分は何者だったのか」と悩む母。何者になることより、だれかにこうして贈与していくことこそが私たちの役割なのだ。
私の子育ても本当に終わったのだと実感した。
もう大丈夫。
この二人はどんなことがっても生きていけるだろう。
そして私の力なんかもはや必要ないほど、多くの人とともに生きていくのだろう。
とってもいい一日でした。
自立について考える~祖母の涙≫







今年私の母、高木淑子さんが88歳の喜寿。
女性の平均寿命が87歳の時代。
病気一つせず、思ったことをズバズバいうところも全く変わることなく顕在。
子どものころから、迫力のある人(ロックともパンクともいう)だとは思っていた。
時には理不尽であったり、はたまた哲学者的であったり。
そして今でも私や妹弟にも多大な影響を与えている。
自分に正直に生きるというのは時に回りも傷つくし、本人も傷つく。それでも忖度なしに前に進む。
生き方としては生きづらいと思う。年をとって少しはおとなしくなったけれど、それでも何かをぶっ壊しても前に進む。(相変わらず理不尽)
(現在、弟と生活しているのだが、どんなに大変かは想像できる。カズさん、ありがとう!)
そいて、10月14日、静岡に住む母を浜松に招いて、主に久保田瑛(孫)夫婦がアテンドしてお祝いの会が設けられた。そして、もう一人の孫である壮(たけし)も参加。
姉からの通達は「おばあちゃんに何かプレゼントを用意すること」
そしてたけしの支援者とたけしでかなり悩んだらしい。
相手は淑子さんである。気に入らなければ「いらない」と突き返される。
さあどうするのか。
浜名湖の景色が一望できるレストランでの会食。お客さんが引いてほぼ貸し切り状態になったところで正装したたけしと今日の支援をしてくれているフキ子さんとヨーイチくんと登場。
そして、レストランが用意してくれたケーキと瑛さんの花束と、そしてたけしから一輪挿しをプレゼント。
その姿に、私も本当に驚いた!
私の知っているたけしじゃない。
淑子さんをじっと見つめているたけし。そこには、28歳の若々しい青年がいた。
「僕はもうちゃんと自立しているよ。おばあちゃん。」と。
なんと凛々しく、たくましいことか。
そして淑子さんが泣いた。
私もほとんど見たことがない母の涙。
それはどんな感情が去来したのかはわからない。
孫二人がちゃんと自分の人生を歩んでいる。もう、子どもではない。
その安どの涙なのか。
特に「障害」についてクラシカルな通念からなかなか脱却できない感情への懺悔なのか。(ここだけは保守的であった)
そして、この会を企画の秀逸さに感嘆した。
瑛はたけしが一人の大人として誰かに「プレゼント」を手渡すことにこだわっていた。
常に庇護を受ける存在ではなく、誰かに何かを「贈与」することの必要性を訴えていた。
話を聞いていてもいまいちピンとこなかったのだが、こういうことだったのか。
誰かに何かを受け渡す。それを自覚的に行うことで初めて「自立」が成立するのか!
そしてこの会と、たけしの一輪挿しは、祖母に確実に何かを手渡した。
それは連綿と続く命のつながりの中に自分もいて、次の人に贈与していくこと。
時に「自分は何者だったのか」と悩む母。何者になることより、だれかにこうして贈与していくことこそが私たちの役割なのだ。
私の子育ても本当に終わったのだと実感した。
もう大丈夫。
この二人はどんなことがっても生きていけるだろう。
そして私の力なんかもはや必要ないほど、多くの人とともに生きていくのだろう。
とってもいい一日でした。
2024年10月10日 21:12

いま新潟に向かっている。明日からの大地の芸術祭見学ツアーに参加する。
大地の芸術祭は今年で9回目を迎えたそうだ。3年に一度開催されているから27年続いている。すごいことだ。私は回2目から見に行っている。そして私の人生において、そして私たち家族にとって、芸術祭との出会いはまさに革命であった。
私の家族には障害者のくぼたたけしがいる。私は芸術の教育を受けていたこともあり、美術館や展覧会など見に行くのが好きだ。しかしたけしが生まれてから、遠出ができなくなった。遠出どころか、365日1日も休むことができない介護の日々が延々と続く生活であった。次第に遠くでやっている展覧会などは見に行けなくなった。
そうした中で唯一、家族で出かけられるのが芸術祭だった。とくに大地の芸術祭は浜松から車で3~4時間で行ける。そして車で回ることができる。そしてほとんどの展示は野外。これはすこぶる我が家には都合がいい。大体静かなところには入ることができないたけし。おとなしくできないからほとんどの美術館や展覧会は難しい。
それに比べて芸術祭はたけしが走ろうが、何かを触ろうが、寝転がろうが、騒ごうが、いっこうに気にしなくていい。少し大きめのキャンプもできるような車(ボンゴブレンディ)に、ブランカ(愛犬:ゴールデンレトリバー)もつれて訪れることを可能にした。我が家族が唯一出かけられる旅行先となった。
思い起こせば、私のたけしとの生活の一番大変な時期に家族で出かけることができた芸術祭は、恐ろしほどの閉塞感の中にある日常から解放され、作品を見ていると本当に生きる力が湧いてきた。その後毎回家族では出かけられなくなっていったが、それで必ず訪れた。
私は芸術祭を通して、本当の意味での芸術を理解していったように思う。ホワイトキューブの中ではない、地域や、風土や様々な課題に対してのアーティストたちの応答に触れることで、芸術の意味や本質を深く考える機会となった。
そしてそれは、私が運営するクリエイティブサポートレッツの活動にも多大な影響力を及ぼしている。障害の人ともに、ただそこにいることをひたすら認め、ともに楽しむことを追求しているレッツ。世間一般の常識とは逸脱していることを疑うことも、ぶれることもなく、ひたすら積み上げてこれたのは、芸術の根幹を学び体感するこうした機会があったからだと思う。
芸術祭は私が受けてきた美術教育とは明らかに違っていたし、たけしというほとんどの常識から逸脱している人と見て回った体験は、芸術の寛容性と豊かさと創造性の可能性を、どんな人でも享受できるものだと確信した。そして、芸術を崇めるでも、ひな壇に飾るものではなく、市井の(私の)日常に息づき、私自身を変え、生きる力となっていくといった、なにものにも代えがたい学びであった。
さあ明日はどんな出会いがあるのだろうか。
私と芸術祭≫

いま新潟に向かっている。明日からの大地の芸術祭見学ツアーに参加する。
大地の芸術祭は今年で9回目を迎えたそうだ。3年に一度開催されているから27年続いている。すごいことだ。私は回2目から見に行っている。そして私の人生において、そして私たち家族にとって、芸術祭との出会いはまさに革命であった。
私の家族には障害者のくぼたたけしがいる。私は芸術の教育を受けていたこともあり、美術館や展覧会など見に行くのが好きだ。しかしたけしが生まれてから、遠出ができなくなった。遠出どころか、365日1日も休むことができない介護の日々が延々と続く生活であった。次第に遠くでやっている展覧会などは見に行けなくなった。
そうした中で唯一、家族で出かけられるのが芸術祭だった。とくに大地の芸術祭は浜松から車で3~4時間で行ける。そして車で回ることができる。そしてほとんどの展示は野外。これはすこぶる我が家には都合がいい。大体静かなところには入ることができないたけし。おとなしくできないからほとんどの美術館や展覧会は難しい。
それに比べて芸術祭はたけしが走ろうが、何かを触ろうが、寝転がろうが、騒ごうが、いっこうに気にしなくていい。少し大きめのキャンプもできるような車(ボンゴブレンディ)に、ブランカ(愛犬:ゴールデンレトリバー)もつれて訪れることを可能にした。我が家族が唯一出かけられる旅行先となった。
思い起こせば、私のたけしとの生活の一番大変な時期に家族で出かけることができた芸術祭は、恐ろしほどの閉塞感の中にある日常から解放され、作品を見ていると本当に生きる力が湧いてきた。その後毎回家族では出かけられなくなっていったが、それで必ず訪れた。
私は芸術祭を通して、本当の意味での芸術を理解していったように思う。ホワイトキューブの中ではない、地域や、風土や様々な課題に対してのアーティストたちの応答に触れることで、芸術の意味や本質を深く考える機会となった。
そしてそれは、私が運営するクリエイティブサポートレッツの活動にも多大な影響力を及ぼしている。障害の人ともに、ただそこにいることをひたすら認め、ともに楽しむことを追求しているレッツ。世間一般の常識とは逸脱していることを疑うことも、ぶれることもなく、ひたすら積み上げてこれたのは、芸術の根幹を学び体感するこうした機会があったからだと思う。
芸術祭は私が受けてきた美術教育とは明らかに違っていたし、たけしというほとんどの常識から逸脱している人と見て回った体験は、芸術の寛容性と豊かさと創造性の可能性を、どんな人でも享受できるものだと確信した。そして、芸術を崇めるでも、ひな壇に飾るものではなく、市井の(私の)日常に息づき、私自身を変え、生きる力となっていくといった、なにものにも代えがたい学びであった。
さあ明日はどんな出会いがあるのだろうか。
2024年06月03日 14:44
インバウンドは街を救わない≫
カテゴリー │レッツ
<
「浜松ちまた会議」浜松の街づくりを考える~インバウンドは街を救わない
6月1日評議員をさせていただいているハウジングアンドコミュニティ財団の交流会があった。本年度採択された20団体が一堂に会して交流する場が近江八幡で開催された。
その中で福祉的な居場所づくりを行っている団体のノミネートも多く、摂食障害、独居、高齢男性、過疎などそれぞれにある課題を居場所として解決していこうという様々な試みの発表もあった。
そもそもこの団体は街づくりへの支援がメインだと認識していたが最近福祉的な案件の応募が多いと聞く。
それはやはり世相を反映していると思うし、行政や制度、既存のコミュニティでは手が届かない隙間を埋めるこうしたNPO的な活動が増えてくるのは仕方がない。
私も毎年助成金をチェックし応募している立場から感じることは、意外にこうした活動を支援してくれるところは少ない。助成金は震災や天災が起こるとそちらへの支援が厚くなる。
恒常的な居場所づくりや社会的な課題をかかえている人のケアは本来は行政や社会福祉協議会、公民館等、公共でできることがたくさんある。
しかしそうはいっても手が入らないから、市民が自助的にやらなくてはいけないようになっている。
レッツの25年のNPO活動でたくさんの心ある市民の活動と接してきた。
しかしやはり継続は難しい。うまく公共と連携してやっている地域もたまにあるが本当に少ない。
そうした課題満載の中で活動を続けるということはやはり並大抵の努力ではできない。
行政に依存するのではなく丁度いい距離感でともに向上していく関係づくりができるのかどうか。
それは私たちの課題でもある。
今回、近江八幡の街並み見学みたいなコーナーもあって街歩きをした。市役所の職員の皆さんの説明で街を1時間ほど歩いた。
近江八幡は太平洋線戦争で爆撃を受けていない。だから街並みや古い建物が残っている。
またそれらの保存活動や改修も市民の自治で行ってきたようだ。市民のプライドが街の景観を守っているといっていい。
しかし、今ここに多くの観光客が訪れている。いわゆるインバウンド。市役所の皆さんのそこは推奨しているようだ。
こういう状況を見ると私は「観光公害」という言葉が頭に浮かぶ。
市民が街づくりを頑張るのは自分の住む街が住みやすくなってほしいから。しかし成功し始めるとそこに観光産業がドカッと入ってくる。
特に行政は経済効果を期待してインバウンドを進める。しかし私はそれにもやもやする。
本当にいい街は住んで暮らしやすいこと。働く場所があって、子育て、介護、文化、といったインフラ整備が整っていて人にやさしい街になること。
そのために税収が必要とよく言われるが、インバウンドは「公害」(ごみ、騒音、環境、治安など)も多いしそれにかかる税金は結局市民が払う。本当に税収がアップしているといえるのか。
もちろん多くの住民が第3次産業に従事している温泉街ならわかるが、普通の市民の生活環境を観光地化していいのか。
浜松の街も商業で成功していた時期があった。その時に多くの住民は郊外に移り住んでいる。
そして人が住まなくなった街は商業だけの街となり、バブル崩壊、リーマンショック等によってあっという間にダメになる。
多様性を言われる時代が到来し、街においても多様な人が群れ、商業だけではなく、居場所、アート・文化、福祉、アメニティなどいろいろな軸が求められている。商業主体のインバウンドでは形成されない。
浜松はものづくりに市民のプライドがある。
行政もスタートアップ、イノベーションなど新しい産業を生むことに力を注いでいる。それが功を奏しているかはよくわからないが、しかしこれを市民は応援しているしそういった新規性、創造性を求めている街だと思う。
浜松市は震災で壊滅的な被害にあった。また地震のことをとても気にしている。
だから歴史的な建造物らしいものがほとんど残っていない。歴史がないというのは文化も同時に消えていく。
一から作っていかなければいけない街だ。
それを新規性の推進力にしてきた街なのかもしれない。
今、重度知的障害者の施設を街中で複数つくりながら、「福祉によるネイバーフット構想」や、「浜松ちまた会議」などいろいろな構想を打ち出している。
それは詰まるところ、自分の住んでいるところをよくする。まず自分たちが快適に住めるよう、暮らせるようにすることの表明でもある。
そして地味なようで、こうした小さな集積がいい街につながっていくのだと思う。
外圧ではなく、主体は私たちだよ。

「浜松ちまた会議」浜松の街づくりを考える~インバウンドは街を救わない
6月1日評議員をさせていただいているハウジングアンドコミュニティ財団の交流会があった。本年度採択された20団体が一堂に会して交流する場が近江八幡で開催された。
その中で福祉的な居場所づくりを行っている団体のノミネートも多く、摂食障害、独居、高齢男性、過疎などそれぞれにある課題を居場所として解決していこうという様々な試みの発表もあった。
そもそもこの団体は街づくりへの支援がメインだと認識していたが最近福祉的な案件の応募が多いと聞く。
それはやはり世相を反映していると思うし、行政や制度、既存のコミュニティでは手が届かない隙間を埋めるこうしたNPO的な活動が増えてくるのは仕方がない。
私も毎年助成金をチェックし応募している立場から感じることは、意外にこうした活動を支援してくれるところは少ない。助成金は震災や天災が起こるとそちらへの支援が厚くなる。
恒常的な居場所づくりや社会的な課題をかかえている人のケアは本来は行政や社会福祉協議会、公民館等、公共でできることがたくさんある。
しかしそうはいっても手が入らないから、市民が自助的にやらなくてはいけないようになっている。
レッツの25年のNPO活動でたくさんの心ある市民の活動と接してきた。
しかしやはり継続は難しい。うまく公共と連携してやっている地域もたまにあるが本当に少ない。
そうした課題満載の中で活動を続けるということはやはり並大抵の努力ではできない。
行政に依存するのではなく丁度いい距離感でともに向上していく関係づくりができるのかどうか。
それは私たちの課題でもある。
今回、近江八幡の街並み見学みたいなコーナーもあって街歩きをした。市役所の職員の皆さんの説明で街を1時間ほど歩いた。
近江八幡は太平洋線戦争で爆撃を受けていない。だから街並みや古い建物が残っている。
またそれらの保存活動や改修も市民の自治で行ってきたようだ。市民のプライドが街の景観を守っているといっていい。
しかし、今ここに多くの観光客が訪れている。いわゆるインバウンド。市役所の皆さんのそこは推奨しているようだ。
こういう状況を見ると私は「観光公害」という言葉が頭に浮かぶ。
市民が街づくりを頑張るのは自分の住む街が住みやすくなってほしいから。しかし成功し始めるとそこに観光産業がドカッと入ってくる。
特に行政は経済効果を期待してインバウンドを進める。しかし私はそれにもやもやする。
本当にいい街は住んで暮らしやすいこと。働く場所があって、子育て、介護、文化、といったインフラ整備が整っていて人にやさしい街になること。
そのために税収が必要とよく言われるが、インバウンドは「公害」(ごみ、騒音、環境、治安など)も多いしそれにかかる税金は結局市民が払う。本当に税収がアップしているといえるのか。
もちろん多くの住民が第3次産業に従事している温泉街ならわかるが、普通の市民の生活環境を観光地化していいのか。
浜松の街も商業で成功していた時期があった。その時に多くの住民は郊外に移り住んでいる。
そして人が住まなくなった街は商業だけの街となり、バブル崩壊、リーマンショック等によってあっという間にダメになる。
多様性を言われる時代が到来し、街においても多様な人が群れ、商業だけではなく、居場所、アート・文化、福祉、アメニティなどいろいろな軸が求められている。商業主体のインバウンドでは形成されない。
浜松はものづくりに市民のプライドがある。
行政もスタートアップ、イノベーションなど新しい産業を生むことに力を注いでいる。それが功を奏しているかはよくわからないが、しかしこれを市民は応援しているしそういった新規性、創造性を求めている街だと思う。
浜松市は震災で壊滅的な被害にあった。また地震のことをとても気にしている。
だから歴史的な建造物らしいものがほとんど残っていない。歴史がないというのは文化も同時に消えていく。
一から作っていかなければいけない街だ。
それを新規性の推進力にしてきた街なのかもしれない。
今、重度知的障害者の施設を街中で複数つくりながら、「福祉によるネイバーフット構想」や、「浜松ちまた会議」などいろいろな構想を打ち出している。
それは詰まるところ、自分の住んでいるところをよくする。まず自分たちが快適に住めるよう、暮らせるようにすることの表明でもある。
そして地味なようで、こうした小さな集積がいい街につながっていくのだと思う。
外圧ではなく、主体は私たちだよ。
2024年04月30日 12:07

アートというのは一種の暴力性を帯びている。そしてアートはそれでいいのだ。その主体はアーティストで、アーティストの思いでどう作ってもいいわけで、その作品の評価はそれを体感した人たちがどう感じるか。特に今までにないものが評価される。それは「新しさ」とか、革新性といわれるものだと思う。
レッツがアートをよりどころにしているのはその革新性に期待していて、つまりは既存の価値観や通念にとらわれない考え方を容認するためにアートをいわば手法のように使っている。
特に障害という一般にはまだまだ認められていない領域に関して、新しい見え方や提案を進めるうえで、このアート的な考え方は非常に有効だと考えている。レッツが福祉事業を行いながら独自のスタンスを維持しているのは、このアートを軸にしていることが大きい。
街づくりに対しても、普通の人が当たり前に街に何らかのかかわりがあるように(自治会活動、町内会活動、地域の掃除、ゴミ出し、清掃作業などを例にとっても)、障害者だからこそ街にコミットするべきだし、彼らの在り方や生き方をインストールしていきたいと思っている。だから2018年、たけし文化センター連尺町ができてからまちに積極的にかかわらろうとしている。
障害者の場合は向こうから誘ってはくれないから、ならばこちらから積極的にかかわろうと試みる。とはいえ、既存の自治会組織などにはなじまないところも多すぎるので、独自のコミュニティを作り出そうとして最近は活動している。
ここに至るにはやはり圧倒的な疎外感と、既存のコミュニティへの居心地の悪さもある。
根本的なずれみたいなものがありすぎて、(特に障害という特性がそうさせている)そこは手を変え、品を変え、果敢にいろいろとフックをつくってきた。そしてその道はまだ始まったばかり(やっている年月は長くても成果は簡単に見えない)
しかしだからと言ってユートピア、楽園をつくりたいのではない。あくまでも一般の人たちと混ざりたいのだ。
自分たちだけが心地いい空間や環境は作りやすい。
しかしそれはいつまでも孤立しているのと変わらない。
多くの人に接してみない限り、自分たちの姿も見えてこないように思う。
混ざり合うことはトラブルも生まれるがしかし結局、それが自由を担保するのだと私は思う。
同族性の強い同じ価値観同士のコミュニティはやはり脆弱で、マンネリ化しやすい。
またちょっとした違いを認めにくい環境をあっという間に作り出す。
結局自由が奪われていく。
私たちの街へのかかわり方は、あくまでもアート的な手法をそこにインストールしているのであって、アート作品として評価されたいとか、認められたいのではなく、ただ単に「仲良くなりたい」だけなのだ。
こんな単純なことをわざわざアート的な手法を持ち込んでやらないといけないのは実は私たちの問題があるのではなく、いわゆる既存のコミュニティの方にある。
少しの違いを認めない、めんどくさい人を排除する、地縁、血縁が大切で排他的。といった特性に私たちは入っていけない。
混ざり合うコミュニテイをどう作っていけるのか。課題である。
まちとアート≫
カテゴリー │レッツ

アートというのは一種の暴力性を帯びている。そしてアートはそれでいいのだ。その主体はアーティストで、アーティストの思いでどう作ってもいいわけで、その作品の評価はそれを体感した人たちがどう感じるか。特に今までにないものが評価される。それは「新しさ」とか、革新性といわれるものだと思う。
レッツがアートをよりどころにしているのはその革新性に期待していて、つまりは既存の価値観や通念にとらわれない考え方を容認するためにアートをいわば手法のように使っている。
特に障害という一般にはまだまだ認められていない領域に関して、新しい見え方や提案を進めるうえで、このアート的な考え方は非常に有効だと考えている。レッツが福祉事業を行いながら独自のスタンスを維持しているのは、このアートを軸にしていることが大きい。
街づくりに対しても、普通の人が当たり前に街に何らかのかかわりがあるように(自治会活動、町内会活動、地域の掃除、ゴミ出し、清掃作業などを例にとっても)、障害者だからこそ街にコミットするべきだし、彼らの在り方や生き方をインストールしていきたいと思っている。だから2018年、たけし文化センター連尺町ができてからまちに積極的にかかわらろうとしている。
障害者の場合は向こうから誘ってはくれないから、ならばこちらから積極的にかかわろうと試みる。とはいえ、既存の自治会組織などにはなじまないところも多すぎるので、独自のコミュニティを作り出そうとして最近は活動している。
ここに至るにはやはり圧倒的な疎外感と、既存のコミュニティへの居心地の悪さもある。
根本的なずれみたいなものがありすぎて、(特に障害という特性がそうさせている)そこは手を変え、品を変え、果敢にいろいろとフックをつくってきた。そしてその道はまだ始まったばかり(やっている年月は長くても成果は簡単に見えない)
しかしだからと言ってユートピア、楽園をつくりたいのではない。あくまでも一般の人たちと混ざりたいのだ。
自分たちだけが心地いい空間や環境は作りやすい。
しかしそれはいつまでも孤立しているのと変わらない。
多くの人に接してみない限り、自分たちの姿も見えてこないように思う。
混ざり合うことはトラブルも生まれるがしかし結局、それが自由を担保するのだと私は思う。
同族性の強い同じ価値観同士のコミュニティはやはり脆弱で、マンネリ化しやすい。
またちょっとした違いを認めにくい環境をあっという間に作り出す。
結局自由が奪われていく。
私たちの街へのかかわり方は、あくまでもアート的な手法をそこにインストールしているのであって、アート作品として評価されたいとか、認められたいのではなく、ただ単に「仲良くなりたい」だけなのだ。
こんな単純なことをわざわざアート的な手法を持ち込んでやらないといけないのは実は私たちの問題があるのではなく、いわゆる既存のコミュニティの方にある。
少しの違いを認めない、めんどくさい人を排除する、地縁、血縁が大切で排他的。といった特性に私たちは入っていけない。
混ざり合うコミュニテイをどう作っていけるのか。課題である。
2024年04月28日 15:52

たけしのてんかん発作。
先日てんかんセンターに受診し、薬物療法では治まらないこと、手術という方法があることが分かった。
18年間苦しんできた、たけしのてんかん発作。
手術という方法はずいぶん前から知っていたのに私はここに興味が持てなかった。というより避けて通ってきたように思う。
それはやはり私にとって、手術、入院っていうのがある種のトラウマになっているからだと思う。
たけしが生まれてすぐ3回の手術があり、ほぼ1年間、入院していた。それは私にとっていい思い出ではない。
同時に私が母親として目覚めた時期でもあったが、まさに崖っぷちの選択をも求められた時期だった。
病院にいて強く思ったことは健康に生んでやれなかったことへの慚愧の思い。今私は障害者の施設をつくり、特に重度知的障害者が社会にいろいろな方法で出る事業を行っている。それは重度知的障害者のありのままの姿を良しとして、そのままで社会に出るべきだと強く思っている。
しかしあの病院という環境下で、たけしの障害は、どうしようもできないことだとわかっていても、なぜこれほどまでに過酷な運命をたけしは背負うことになってしまうのか、そして健康に生んでやれなかったことに対しての申し訳なさみたいな感情を抱いていたように思う。そして病室という暗い空間の中で徹底的に慚愧の思いを味わったがゆえに、ならば明るく楽しく生きていこう!と、その後覚悟が決まる、まさに出発点みたいなものがたけしと私の入院生活にはある。
だから、手術、入院と聞くと、あの時の私の姿がフラシュバックする。
できれば避けて通りたいと思っていたことは事実だろう。
しかし今たけしは自立している。そしてこれは私の人生ではなく、たけしの人生であること。
あの頃1歳にも満たないわが子とは全く違う。28歳の自立した青年なのだ。
私が決めることではない。
もちろんたけしが発語するわけでも、こうしたいと意思表明できるわけではないが、しかし、たけしだったらどうしたいのか、どう生きたいのか。
幸いたけしの周りには多くの支援者やたけしを友人のように思っている人々が大勢いる。
あのころと違って、たけしはちゃんと社会で生きている。
たけしの選択がどういうものなのかはわからないとしても、皆で考えていけばいいのだ。
たけしのてんかん発作2~親じゃ決めれないたけしの将来≫

たけしのてんかん発作。
先日てんかんセンターに受診し、薬物療法では治まらないこと、手術という方法があることが分かった。
18年間苦しんできた、たけしのてんかん発作。
手術という方法はずいぶん前から知っていたのに私はここに興味が持てなかった。というより避けて通ってきたように思う。
それはやはり私にとって、手術、入院っていうのがある種のトラウマになっているからだと思う。
たけしが生まれてすぐ3回の手術があり、ほぼ1年間、入院していた。それは私にとっていい思い出ではない。
同時に私が母親として目覚めた時期でもあったが、まさに崖っぷちの選択をも求められた時期だった。
病院にいて強く思ったことは健康に生んでやれなかったことへの慚愧の思い。今私は障害者の施設をつくり、特に重度知的障害者が社会にいろいろな方法で出る事業を行っている。それは重度知的障害者のありのままの姿を良しとして、そのままで社会に出るべきだと強く思っている。
しかしあの病院という環境下で、たけしの障害は、どうしようもできないことだとわかっていても、なぜこれほどまでに過酷な運命をたけしは背負うことになってしまうのか、そして健康に生んでやれなかったことに対しての申し訳なさみたいな感情を抱いていたように思う。そして病室という暗い空間の中で徹底的に慚愧の思いを味わったがゆえに、ならば明るく楽しく生きていこう!と、その後覚悟が決まる、まさに出発点みたいなものがたけしと私の入院生活にはある。
だから、手術、入院と聞くと、あの時の私の姿がフラシュバックする。
できれば避けて通りたいと思っていたことは事実だろう。
しかし今たけしは自立している。そしてこれは私の人生ではなく、たけしの人生であること。
あの頃1歳にも満たないわが子とは全く違う。28歳の自立した青年なのだ。
私が決めることではない。
もちろんたけしが発語するわけでも、こうしたいと意思表明できるわけではないが、しかし、たけしだったらどうしたいのか、どう生きたいのか。
幸いたけしの周りには多くの支援者やたけしを友人のように思っている人々が大勢いる。
あのころと違って、たけしはちゃんと社会で生きている。
たけしの選択がどういうものなのかはわからないとしても、皆で考えていけばいいのだ。
2024年04月28日 14:11

ヘルパーのサメちゃんがとってくれた写真
たけしとてんかん発作1
先日てんかんセンターに受診した。
10歳から始まったてんかんは、本当に悩みで、薬の副作用に苦しんだ挙句、3年前に薬を変える決心をした。そこから主治医と相談しながら微調整してきたが発作は治まらない。1日も5回も6回も軽い発作が起こる。
副作用に苦しんでいたころよりは、表情もよくなったが(結局薬を少なくしているってことなんだけど)、今度は意識が飛ぶ発作を繰り返ようになってしまった。特に後ろにスローモーションのように倒れていくので転倒の危険がある。
去年は打ちどころが悪くて腰の骨を折ってしまった。
発作を抑えるためには薬を飲めばいいのだが、そうすると1日中ボーとしている。午前中寝ているみたいなことがしょっちゅう起こる。表情もさえない。まさに生活の質が下がる。
発作と生活の質。どの辺を塩梅と考えればいいのかを今の主治医以外のご意見も聞いてみようと、てんかんセンターを受診することにした。
てんかんは薬物療法のほかに、手術、食事療法などいくつかある。むしろ薬物療法を2年やっても治まらなかったり、副作用が激しい場合は薬物療法では無理と判断し、そのほかの方法を考えるのが通例。(18年間薬物療法やり続けたたんだけど・・・)そしてたけしみたいの強度行動障害があって多動で、指示に従えない人であっても手術は可能とのことだった。
手術と簡単に言うけれどそれはそれで大変なので、その辺の判断(覚悟?)ができた段階で、手術については改めて説明するが、どうするか決めてくれとのことで診察は終わった。
鼻っから手術はできないものと思っていたし、薬物療法でなんとかならないのかと考えていたのでまさに青天の霹靂!
というか甘かった~。
今の主治医の先生にも手術の話は聞いていたけれど、私自身がたけしには手術は無理と思い込んでいたからあまり真剣に考えたことがなかった。
10歳から苦しんできたてんかん発作。
いわゆる頭の中の電気信号のエラーだからその元を取り除いてしまえばいいといういたって単純なこと。もちろん頭を勝ち割って手術するのだからどう考えてもリスクはあるだろう。しかし、小さいころから急に怒りだしたり、荒れたりするのはたけしの性格ではと思っていたが実は、この電気信号のエラーのせいかもしれない・・・。
そして1日に5回も6回も倒れていると本人は相当体力も使うだろうし、脳も疲れるだろう。こんなこと何度も繰り返しているとどこか傷んでくる。
最近私はたけしとは週末に一緒に過ごすだけだから圧倒的にヘルパーやレッツのスタッフと生活している。これは支援会議ものですな。
それにしてもつくづく、たけしってフロンティアだと思う。
レッツができたのも、アルス・ノヴァができたのも、浜松で知的障害者でたぶん第1号で重度訪問介護を使って自立生活を始めたのも、それに合わせてヘルパー事業をレッツで始めなければいけなくなったのも、シェアハウスができたのも、全部たけし。
誰もやったことがないことを次々とチャレンジしていく。まさに道を開いていく人。
今回もどう考えても一筋縄でいかない手術に挑戦するべきなのか。しかしそれ以外に彼のクオリティ・オブ・ライフを実現するすべがあまり見いだせない状況の中で(いつもそうだが後がないから挑戦するしかなくなるのだが・・・)どうしたらいいのだろうか。
いやはや。悩みが一つ増えました。
ホント。いつになったら解放されるのやら。
気が重い~。
たけしとてんかん発作1≫

ヘルパーのサメちゃんがとってくれた写真
たけしとてんかん発作1
先日てんかんセンターに受診した。
10歳から始まったてんかんは、本当に悩みで、薬の副作用に苦しんだ挙句、3年前に薬を変える決心をした。そこから主治医と相談しながら微調整してきたが発作は治まらない。1日も5回も6回も軽い発作が起こる。
副作用に苦しんでいたころよりは、表情もよくなったが(結局薬を少なくしているってことなんだけど)、今度は意識が飛ぶ発作を繰り返ようになってしまった。特に後ろにスローモーションのように倒れていくので転倒の危険がある。
去年は打ちどころが悪くて腰の骨を折ってしまった。
発作を抑えるためには薬を飲めばいいのだが、そうすると1日中ボーとしている。午前中寝ているみたいなことがしょっちゅう起こる。表情もさえない。まさに生活の質が下がる。
発作と生活の質。どの辺を塩梅と考えればいいのかを今の主治医以外のご意見も聞いてみようと、てんかんセンターを受診することにした。
てんかんは薬物療法のほかに、手術、食事療法などいくつかある。むしろ薬物療法を2年やっても治まらなかったり、副作用が激しい場合は薬物療法では無理と判断し、そのほかの方法を考えるのが通例。(18年間薬物療法やり続けたたんだけど・・・)そしてたけしみたいの強度行動障害があって多動で、指示に従えない人であっても手術は可能とのことだった。
手術と簡単に言うけれどそれはそれで大変なので、その辺の判断(覚悟?)ができた段階で、手術については改めて説明するが、どうするか決めてくれとのことで診察は終わった。
鼻っから手術はできないものと思っていたし、薬物療法でなんとかならないのかと考えていたのでまさに青天の霹靂!
というか甘かった~。
今の主治医の先生にも手術の話は聞いていたけれど、私自身がたけしには手術は無理と思い込んでいたからあまり真剣に考えたことがなかった。
10歳から苦しんできたてんかん発作。
いわゆる頭の中の電気信号のエラーだからその元を取り除いてしまえばいいといういたって単純なこと。もちろん頭を勝ち割って手術するのだからどう考えてもリスクはあるだろう。しかし、小さいころから急に怒りだしたり、荒れたりするのはたけしの性格ではと思っていたが実は、この電気信号のエラーのせいかもしれない・・・。
そして1日に5回も6回も倒れていると本人は相当体力も使うだろうし、脳も疲れるだろう。こんなこと何度も繰り返しているとどこか傷んでくる。
最近私はたけしとは週末に一緒に過ごすだけだから圧倒的にヘルパーやレッツのスタッフと生活している。これは支援会議ものですな。
それにしてもつくづく、たけしってフロンティアだと思う。
レッツができたのも、アルス・ノヴァができたのも、浜松で知的障害者でたぶん第1号で重度訪問介護を使って自立生活を始めたのも、それに合わせてヘルパー事業をレッツで始めなければいけなくなったのも、シェアハウスができたのも、全部たけし。
誰もやったことがないことを次々とチャレンジしていく。まさに道を開いていく人。
今回もどう考えても一筋縄でいかない手術に挑戦するべきなのか。しかしそれ以外に彼のクオリティ・オブ・ライフを実現するすべがあまり見いだせない状況の中で(いつもそうだが後がないから挑戦するしかなくなるのだが・・・)どうしたらいいのだろうか。
いやはや。悩みが一つ増えました。
ホント。いつになったら解放されるのやら。
気が重い~。
2023年12月24日 21:31
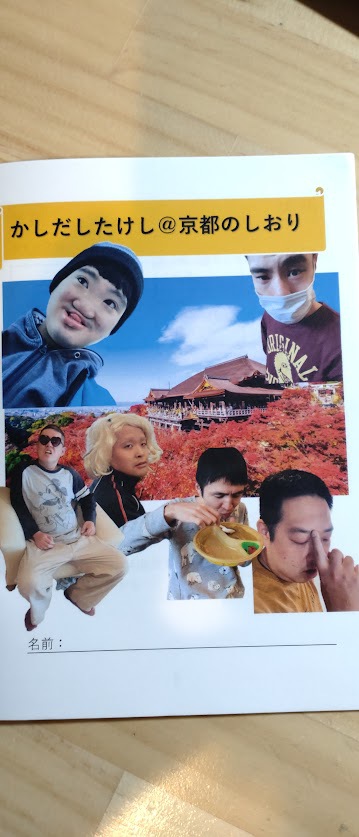
明日から京都大学にかしだしたけし!
アルス・ノヴァ(レッツの運営する障害者施設)でも、ツワモノばかり6人が出張します!
そして年齢関係なく、新入社員+かたりノヴァ担当者8人がサポートします!
どんな道中になるのやら。
セレナ2台で行くのですが、なにせ、100キロ超えの利用者3名がいるので、パンパン。
なので私は新幹線。
それにしても、脱走するかもしれない利用者や、何処かに走り出してしまう利用者もいて、スタッフはホテルの入口に寝るかとか、内側から鍵がかかるホテルはないのかとか、GPS機能付きスマホを買ってきたりと大あらわです。
いや〜。楽しい。
何をするかわからん面々。どんな旅になるでしょうか。
そしてエリートと言われている京大生は、重度知的障害者にあったこともないと思います。
障害者がいいとか悪いとか、怖いとか、嫌とか、そういうのも含めて、出会わないとわからない。
今回、わざわざスペシャルな彼らに参戦?してもらうのは、若い学生さんに何かを伝えて欲しいと思うから。
世間で言われているほど彼らはかわいそうではいし、みんなのびのびしていて、自由に生きている。そして、こういう人もいるし、こういう生き方があるんだということを伝えたい。
阻害も差別も、ほとんど「知らない」ことから始まる。
そして、今世界で起こっている戦争の根幹もおなじ。
障害者とか、異国民とか、異教徒ではなくて、たけしくん、こうすけくん、しゅんくん、りょうがくん、ゆうじくん、りょうくん、という個人と接すれば、人はリアルに感じるし交流する。
その体感が必要。
それがいろいろなことを超えていく力になると私は思ってます。
かしだしたけし考1≫
カテゴリー │レッツ
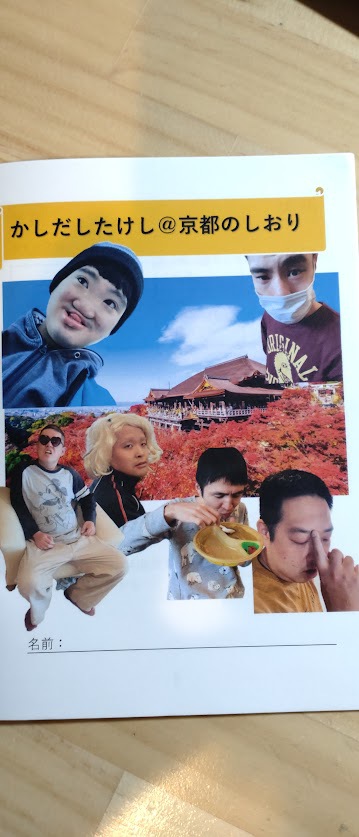
明日から京都大学にかしだしたけし!
アルス・ノヴァ(レッツの運営する障害者施設)でも、ツワモノばかり6人が出張します!
そして年齢関係なく、新入社員+かたりノヴァ担当者8人がサポートします!
どんな道中になるのやら。
セレナ2台で行くのですが、なにせ、100キロ超えの利用者3名がいるので、パンパン。
なので私は新幹線。
それにしても、脱走するかもしれない利用者や、何処かに走り出してしまう利用者もいて、スタッフはホテルの入口に寝るかとか、内側から鍵がかかるホテルはないのかとか、GPS機能付きスマホを買ってきたりと大あらわです。
いや〜。楽しい。
何をするかわからん面々。どんな旅になるでしょうか。
そしてエリートと言われている京大生は、重度知的障害者にあったこともないと思います。
障害者がいいとか悪いとか、怖いとか、嫌とか、そういうのも含めて、出会わないとわからない。
今回、わざわざスペシャルな彼らに参戦?してもらうのは、若い学生さんに何かを伝えて欲しいと思うから。
世間で言われているほど彼らはかわいそうではいし、みんなのびのびしていて、自由に生きている。そして、こういう人もいるし、こういう生き方があるんだということを伝えたい。
阻害も差別も、ほとんど「知らない」ことから始まる。
そして、今世界で起こっている戦争の根幹もおなじ。
障害者とか、異国民とか、異教徒ではなくて、たけしくん、こうすけくん、しゅんくん、りょうがくん、ゆうじくん、りょうくん、という個人と接すれば、人はリアルに感じるし交流する。
その体感が必要。
それがいろいろなことを超えていく力になると私は思ってます。
2023年12月24日 21:28

名前のヤバさは別として、重度知的障害の面々が押しかけることに意味がある。
そして4日は、クリストファー大学の阪本先生に頼まれている講義に参加します。
看護学生90名、その他福祉系の学生さん40名の前で、アルス・ノヴァのメンバーがいつもの日常を繰り広げます。
実はここが彼らのすごいところ。
りょうがくんはいつものようにカキカキして、雄叫びを発するだろうし、
ゆうじくんはいつものように揺れるだろうし、
こうすけくんはいつものように短い単語を発しながら動ごきまわるだろうし、
りょうくんは、いつものように寝そべるだろうし、
しゅんちゃんは、いつものようにポータブルで音を聞いているだろうし、
たけしは、いつものように、入れ物をカチャカチャするだろうし、
これをどこでも、何時でもできることが彼らの凄いところだと私は思います。
普通は忖度したり、意識したり、緊張したり、萎縮するものなんだけど。
そうやって、のびのびできるのは、そういった行動をいつも止めていないレッツだからだとは思うけれど、その揺るぎない行動の所以はそれぞれにある。
人の行動はその周りの環境で、正しくも悪くもなリますね。
だからその環境の設定を変えることで多くの人が居やすくなるとも言える。
そんなことを伝えにいってきまーす。
かしだしたけし考2≫
カテゴリー │レッツ

名前のヤバさは別として、重度知的障害の面々が押しかけることに意味がある。
そして4日は、クリストファー大学の阪本先生に頼まれている講義に参加します。
看護学生90名、その他福祉系の学生さん40名の前で、アルス・ノヴァのメンバーがいつもの日常を繰り広げます。
実はここが彼らのすごいところ。
りょうがくんはいつものようにカキカキして、雄叫びを発するだろうし、
ゆうじくんはいつものように揺れるだろうし、
こうすけくんはいつものように短い単語を発しながら動ごきまわるだろうし、
りょうくんは、いつものように寝そべるだろうし、
しゅんちゃんは、いつものようにポータブルで音を聞いているだろうし、
たけしは、いつものように、入れ物をカチャカチャするだろうし、
これをどこでも、何時でもできることが彼らの凄いところだと私は思います。
普通は忖度したり、意識したり、緊張したり、萎縮するものなんだけど。
そうやって、のびのびできるのは、そういった行動をいつも止めていないレッツだからだとは思うけれど、その揺るぎない行動の所以はそれぞれにある。
人の行動はその周りの環境で、正しくも悪くもなリますね。
だからその環境の設定を変えることで多くの人が居やすくなるとも言える。
そんなことを伝えにいってきまーす。


